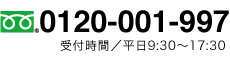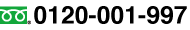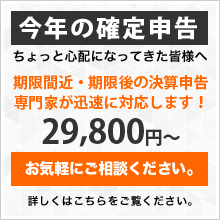新社長のための「労働保険の基本知識」

今回のテーマ「労働保険」について説明させていただきます、東京都台東区のクラウドに強い税理士・公認会計士の白根と公認会計士の長瀬です。皆さまに抑えておいていただきたい労働保険の知識のうち、会社を設立したばかりの社長に知っておいていただきたい基本知識をご案内するコラムです。
この知識は個人事業主・法人共通ですので、経営にとても重要です。
<目次>
1. 概要
2. 労働保険の対象者
3. 労働保険の加入手続
4. 労働保険の更新手続
5. まとめ
会社を設立したばかりの社長に知っておいていただきたい基本知識(労働保険)
1. 概要
「労働保険」とは(1)「労災保険」と(2)「雇用保険」をまとめたものをいいます。
いずれも「事業主と労働者を労働上のトラブルから守る」というものです。具体的にどのような内容の保険かを確認していきましょう。
(1) 「労災保険」
業務上又は通勤中のケガや病気をした際、事業主は労働基準法により療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償などを行なう義務が有ります。事業主はこれらの補償の負担が必要となり、時には事業の継続を脅かすほど巨額になることもあります。 万が一の労働災害の補償をするのが労災保険となります。
原則として従業員を雇用している事業所は法人、個人を問わず、適用事業所となります。
(2) 「雇用保険」
よく失業保険と呼ばれます。労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる理由が生じた場合に必要な給付を行います。しかし、労働者の失業時の保険だけではありません。
事業主が労働者の雇用維持を図るための助成、労働者を新規に雇うための助成、労働者の処遇や職場環境の改善を図る助成などを行う保険でもあります。
2. 労働保険の対象者
(1) 労災保険の対象者
常用・日雇・パート・アルバイトなどの雇用形態に関わらず、労働の対価で賃金を受ける全ての方が対象となります。つまり、一人でも雇った場合には、労災保険に加入しなければなりません。
会社の代表者や役員については対象者とはなりません。
(2) 雇用保険の対象者
雇用保険の対象者は原則として次のいずれの要件も満たす方です。
・31日以上の雇用見込みがあること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
なお、会社の代表者や役員は雇われる立場ではありませんので、雇用保険の対象外です。ただし、出向などで親会社との雇用関係が続いたまま子会社の代表取締役になっている場合は、親会社との雇用関係において被保険者となる場合があります。役員も同様で、従業員としての身分であって、給料の支払い状況も労働者性も高い場合は雇用保険の被保険者となります。
3. 労働保険の加入手続
労働保険に加入する場合の手続について、加入書類の記入や添付資料の準備が必要です。
なお、(1)労災保険と(2)雇用保険で手続きの所轄が異なりますのでご注意下さい。
また、手続の順番は(1)労災保険と(2)雇用保険の順番になります(雇用保険の手続きには、労働基準監督署で先に労働保険番号の交付を受けることが必要です。)。
(1) 労災保険の手続
①提出資料
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
・履歴事項全部証明書(写)1通
②書類の提出先
管轄の労働基準監督署
③提出期限
保険関係の設立した日の翌日から10日以内
(※)厳密には、労働保険概算保険料申告書は保険関係の成立した日の翌日から50日以内の提出ですが、実務的には労働保険関係成立届と同時に提出し、50日以内に保険料を納付します。
(2) 雇用保険の手続
①提出書類
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
・労働保険関係成立届(控)⇒労働基準監督署受理済みのもの
・労働保険概算保険料申告書(控)
・履歴事項全部証明書 原本1通
・労働者名簿
②書類の提出先
所轄の公共職業安定所(ハローワーク)
③提出期限
従業員を雇った日の翌日から10日以内
(※)厳密には、雇用保険被保険者資格取得届は従業員を雇った日の翌月10日以内の提出ですが、実務的には他の書類と同時に提出します。
4. 労働保険料の納付
(1) 初年度
①内容
労働保険の保険料は、毎年4月1日~翌年3月31日の1年間を単位として計算します。
保険料は全ての労働者(雇用保険の場合は、被保険者)に支払われる年間賃金総額に、事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
②提出書類
前述の「3. 労働保険の加入手続」で対応済みとなります。
③書類の提出先
前述の「3. 労働保険の加入手続」で対応済みとなります。
④申告書提出・納付期限
前述の「3. 労働保険の加入手続」で対応済みとなります。
(2) 2年目以降(労働保険の更新)
①内容
労働保険料は、4月1日から翌年3月31日期間の保険年度ごとに計算して納めることになっています。
初めに1年分の保険料を前払いし、賃金総額が確定した翌年度に前払保険料と保険料実績との過不足を精算するしくみです。
毎年度行う、前年度の保険料の精算(確定保険料の申告・納付)と新年度の保険料の申告(概算保険料の申告・納付)を労働保険の更新といいます。
②提出書類
・労働保険概算保険料申告書(継続事業)
③書類の提出先
所轄都道府県労働局、労働基準監督署、金融機関のいずれか
④申告書提出・納付期限
原則として、労働保険料の申告・納付期限は、7月10日です。
ただし、概算保険料が40万円以上(労災保険又は雇用保険のいずかれ一方のみ加入の場合は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、3回に分けて納付(延納)することができます。納付期限は下記の通りです。
<概算保険料が40万円以上の場合>
第1回:7/10、第2回:10/31、第3回:1/31
<労働保険事務組合に委託している場合>
第1回:9/6、第2回:11/14、第3回:2/14
(参考)
厚生労働省HP 労働保険の年度更新とは
厚生労働省HP 労働保険料の申告・納付
5. まとめ
いかがでしたでしょうか。
従業員を雇うと多くの手続きが必要になります。労働保険は法的な加入義務はもちろん、労使ともに安心して仕事をするために大変重要なものです。従業員を雇われた場合や現時点で未加入となっている場合には、早速確認しましょう。